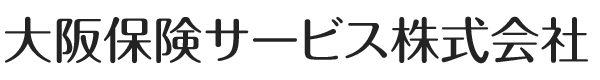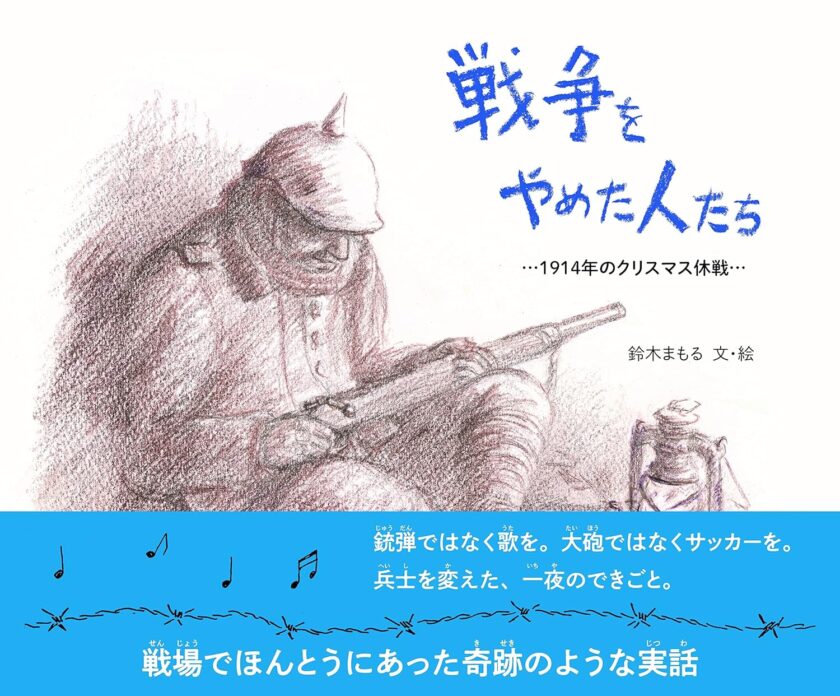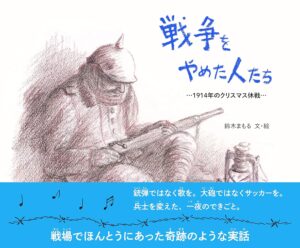「あなたを押しのけて私は生きる」
藤木正三著『神の風景』(ヨルダン社)
結局このような生き方を私たちはしています。
そうでもしなければ生きてゆけないとよく言われますし、確かにその生き方で獲得することは多いのです。
しかし、獲得の喜びと命の喜びとは別であることに注意しましょう。
獲得の中で生命はむしろ不完全燃焼をかこっているのではないでしょうか。
蝋燭が他を照らしながら自分自身は消滅してゆくように、燃焼とは本来他に仕えることなのです。
「あなたが生きれば私も生きる」これはお人好しではありません。
燃焼を求める生命の訴えなのです。
他人を押しのけてまで生きようとした記憶はありません。
はたしてこのように言いきれるだろうか。
中学生の一時期、必死にテスト勉強しました。
それは、単に学ぶという思いではなく、良い点をとって「オレはできるんだ」と能力を誇示したい面があったことは否めません。
大した能力がなかったので、他人に自分の能力を示すことも、大した歓心を買うことも、まして権力を持つこともありませんでした。
もし私に優れた運動能力があれば、人を押しのけて全国大会に出場し世界を目指したかもしれません。
音楽的才能があればショパンコンクールを目指したかもしれません。
何かが出来ることは人を生きやすくします。
持っていることも同じです。
世間の評価も受けます。
そして他人の評価が自己肯定感に繋がると錯覚し、とりあえず生きる自信を持つのです。
しかし、それだけではなく、出来るようになること自体喜びです。
Ave Verum Corpusにチャレンジして弾けるようになった時、「やった!」という何とも言えない感情がありました。
そこには他人の評価はありません。
老齢期になりましたが、まだ走ることができます。
「今日も走れた」一人で拍手しています。
坂を上っていくような生き方はしませんが、坂を下りつつもピアノやランニングにチャレンジし続けます。
蝋燭が他を照らしながら自分自身は消滅してゆくように生きるのはもう少し後にします。